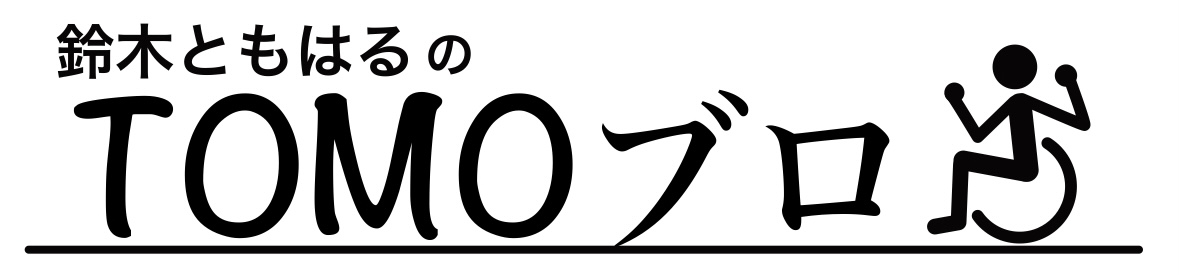皆さんは、日本の旧石器時代の生活に対するイメージはどのようなものですか?
野性的で質素で粗末。世界と比較すると圧倒的に後進的な生活を送っていたと思う方も多いのではないでしょうか。
日本には旧石器時代の遺跡が1万4500カ所あるのですが、その多くの場所で出土している「ある」ものが、世界中の考古学者から「世界最古の文明は日本にあった」と言わせてしまうきっかけになりました。
その「ある」ものが「黒曜石」です。
ご存知の通り黒曜石は、旧石器時代や縄文時代には槍先や矢じりとして使用されていて、日本各地の遺跡から出土している身近な石器です。
しかし、採石することが出来る場所はというと何処でも採れるわけではありません。また、産地によって微量成分が異なるため、対象とする黒曜石を調べれば産地を特定することが出来るのです。
国内の遺跡から出土した黒曜石を調べてみると、最も古いものは3万8000年前に採石していたことが分かったのですが、注目されたのはその産地です。
それらの中に、伊豆諸島の「神津島」で採石したものが大量に含まれていることが分かったのです。更に、それらの黒曜石は日本各地の遺跡から出土していることも分かりました。
3万8000年前は、現在の氷河期の氷期(現在は氷河期の中でも暖かい間氷期)にあたり、海面は今よりも120m以上低い位置にありました。
そのため、日本列島と大陸は陸で繋がっていたのですが、神津島と日本列島の間は水深が深く決して陸続きになる事はありませんでした。
つまり、伊豆半島の南端から50キロメートル以上離れた神津島まで、当時の日本人は黒曜石を採石するために何度も舟を出していたことになり、これが現時点で確認されている人類史上最古の往復航海の痕跡とされています。
また、神津島で採れた黒曜石が日本だけではなく、大陸でも発見されていることから、3万8000年前には広い地域の人々と交易を行うことのできる流通網が、既に存在していたと考えられています。
これはほんとにすごいことです。
なぜならば、往復航海を行うには高度な航海技術が必要になります。ましてや神津島のある周辺には、世界一流れの速いとされている黒潮が流れており、その黒潮を突っ切り神津島まで行くことは至難の業と言えます。
たとえ流されたとしても、星を読み戻ることが出来なければ、体力のある勇猛果敢な男子を一度に多く失うことになり、高度な操船技術は既に持っていたと考えられます。
また、国内外に確立された流通網は、交易を行いたい者とその地域の者との間に共通の利益や価値観、理解や友好的な関係がなくては実現はしませんし、情報交換も頻繁にあったと考えられます。
これらを踏まえると、旧石器時代の日本には、私たちが今まで考えもしなかった高度の技術を持ち、平和で情報を共有した文明が存在したかもしれませんね。
あなたはどう思いますか?