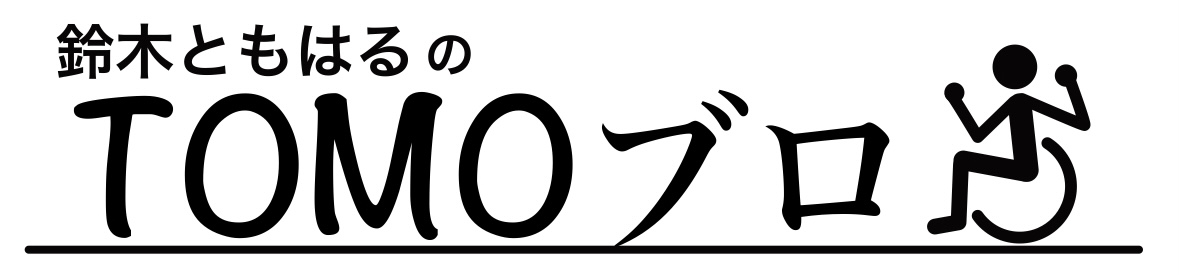【先祖の話⑥】
約1万8000年前より、現在の氷河期は氷期から間氷期に変動し、地球の気温が上がると共に海面が120m以上上昇。
それまで大陸と陸続きだった日本は、四方を海で囲まれ日本列島となりました。(因みに120m海抜が低かった氷期は、日本の北側と大陸は繋がっていましたが、朝鮮半島と日本はつながっていなかったようです。)
日本列島では、大陸からの侵略を受けにくく、豊かな海洋資源と温暖で湿潤な気候による森林資源に恵まれ、あえて農耕を行う必要がありませんでした。
そのため、領地という意識が低く、人々は土地をめぐり争う必要がなかったと考えられています。
アフリカの豊かな森に住む動物達は、他の動物や群れに対して縄張りを主張し威嚇することが他の地域の動物達よりも少ないと報告されていますが、私たちの先祖が、日本で1つの場所に長期にわたり定住することができたのは、食料を分かち合えるほど、とても住みやすい環境があったからなのでしょう。
そして、驚きの発見は更に続きます。
それが、日本人の主食とされる「米」です。
私も含めて多くの人は、「稲作は、弥生時代に渡来人とともに日本にもたらされた」と習ったのではないでしょうか。
確かに、水田を整え稲を育てる「水稲」の技術は弥生時代に大陸より伝えられたものなのですが、稲自体は縄文時代に既に日本にあったとする見方が有力となって来たのです。
日本の稲作の起源を考える上で重要な考古学的証拠とされるのが、縄文遺跡から採取された稲のプラントオパール(植物珪酸体)です。
プラントオパールとは、イネ科植物(特に稲)の葉や茎に含まれるケイ酸が化石化したガラス質の微粒子で、植物が枯れた後も土壌中に残ります。そのため、稲作の存在や栽培時期を推定する手がかりとなるものです。ただし、風や土壌攪拌による混入の可能性があり、年代特定には慎重な分析が必要となります。
このプラントオパールが、複数の縄文遺跡から見つかっており、特に岡山県の彦崎貝塚では、6000年前の地層から稲のプラントオパールが土壌1gあたり2000〜3000個と大量に検出されました。
このことは、縄文時代の大量発見としては日本初で、これまで稲作は4000年前の縄文時代後期から始まったとされていましたが、6000年前のプラントオパールは稲作開始時期を大幅に遡らせる可能性を示しています。
また、水田を整備した痕跡が見つかっていないため、当時は米がまだ主食ではなく、補助的な役割として畑作による陸稲(熱帯ジャポニカ)の栽培が行われていたと推定されています。
これはすごい発見ですよね。
稲作以外にも集落の周辺には、それまであった木々を伐採しクリやドングリの木を積極的に植林した痕跡の残る遺跡も確認されています。
これまで、縄文時代の私たちの先祖は、原始的で狩猟・採集・漁労を中心とした生活を営み、まだ農耕は起こっていなかったとされてきました。
しかし、日本は地政学的にみても、大陸からの距離、大きさ、形状(日本の70%は山間部←これがかなり重要)、位置など奇跡的な立地にあり、自然が豊かだったために縄文時代の人々は農耕を行う必要がありませんでした。
主食は、単一のものは存在せず、堅果(クリ、ドングリ)、魚介類(サケ、貝)、狩猟肉(シカ、イノシシ)、根菜・果実で、地域や季節により多様な食材を選んでいました。
しかし、食物の栽培を全く行ってこなかったわけではなく、厳しい冬を乗り越える備蓄など補助的な役割として陸稲(熱帯ジャポニカ)などの農作物を上手く取り入れていたようです。
縄文時代のイメージがずいぶん変わりますよね。